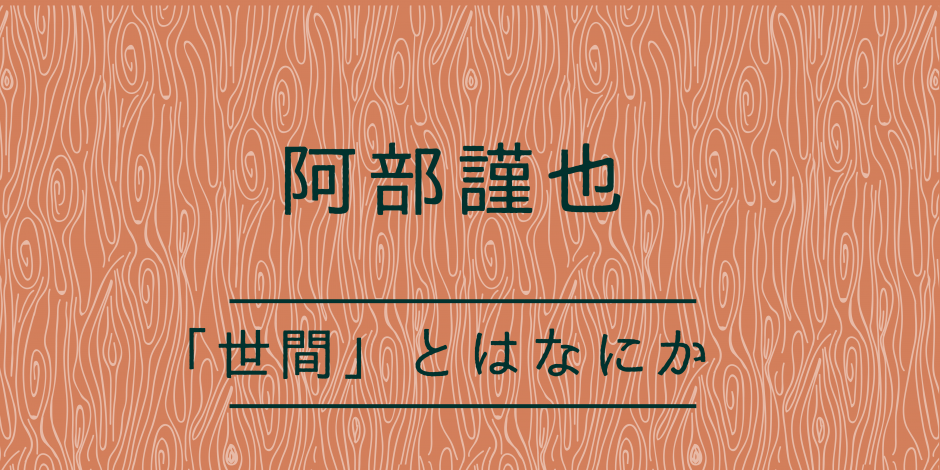日本の歴史学者に阿部謹也という人がいます。1935生まれでヨーロッパ、主にドイツの中世史を専門にした方です。阿部謹也は幼少の頃に父を失い、戦後すぐにカトリックの修道院で生活していたという経験から、中世の修道院の研究から歴史学の研究に入っていきました。私が阿部謹也という人を興味深いと思うのは、時代とその人が育ってきた背景と学問が一致しているように思える点です。阿部は自伝において、上原専禄という歴史学者に出会うことから、歴史学が単に歴史的な事実を扱うのではなく、「歴史意識」というのが個人の内面とつながっていて、それこそが歴史的に作られているという考える至ったようです。一方、学生運動の中で一般の人々に全く関心をもってもらえなかったという経験を持った阿部は、ヨーロッパの歴史を研究することと、日本の「世間」について考えることを常に並行していたようです。今回取り上げる『「教養」とは何か』という本などはその題名からは、学者が書いた啓蒙書という感じを受けますが、阿部謹也がやろうとしていたことをはもっと、本質的な考察であるように見受けられます。依頼した出版社の意図としては読みやすい教養に関する本を、ということだったのでしょうが、阿部自身は自身の研究と深く結びつけることで、ヨーロッパ的な「教養」に対して日本的な「世間」の弱点を描き出そうとしていることはなかなかに興味深いところです。
阿部謹也の仕事とは歴史学というにはアカデミックな方法からは少し離れているようにも思います。当時の文献を読み込み、過去にあった事実について考察を加えていくという点にはおいては、阿部謹也はアカデミックな仕事をしていたと言えるでしょうか、その他にも阿部謹也は多くの一般向けの著作を書いています。それはどうも、学者が出版社に頼まれて啓蒙書を書くというよりは、阿部自身の探求によって得られた考察と考えて良いものでしょう。自伝を読む限り、阿部は日本人の生活意識と歴史意識を考えることで、なぜ日本において個人が社会を客観的に見る力が弱いのかを考え、それを「世間」という言葉で表現しました。日本人にとって社会で常識を教えてくれる「正しさ」は個人が知識や経験を身につける以上に、「世間」と呼ばれる見えない存在が、あたかも社会的現実を知っていて、それを人々が内面かしているようになっている。阿部謹也はヨーロッパの歴史の中で生活意識が変化していくことを専門であるヨーロッパ中世史において論じる一方で、ヨーロッパようではなかった日本、ということを「世間」という言葉で論じました。「世間」は狭いものであり、それは限られた人間関係による支配です。簡単にいってしまえば、主体としての個人が薄く、関係性のなかで意見と決めてしまう日本人というステレオタイプにもなってしまいますが、阿部の考察を読んでいると単純にステレオタイプと切って捨てることもできないように思います。阿部謹也がほとんどヨーロッパについて述べずに日本の歴史を振り替えて「世間」について述べたのが『「世間」とは何か』という本です。本書で阿部は万葉集や吉田兼好、親鸞、井原西鶴、漱石、永井荷風という人々の言葉を例に、日本の個人と社会の変化を論じています。
阿部謹也が個人のない日本ということを論じるとき、似たタイプとして挙げられることがあるのが『アイスランドサガ』です。アイスランドサガはもともと無人島だったアイスランドに主としてノルウェー人が移住してきた頃の出来事が物語形式で残されたものです。サガには集団同士の争いについての説明があるようでなのですが、そこには個人が存在せず、個人と集団は一体であるように書かれているそうです。これは集団に個が埋没している状態ですが、ある意味では、現在のような経済システムを主として全てが個人主義化している社会から遠い、初期の社会形跡期においては、社会がこのような集団主義的な性質を持つことは当然だと思われます。西洋はキリスト教文化、あるいは人々の移動、支配関係の変化のなかで個人が形成されるわけですし、日本の場合も必ずしもサガの時代と同様の集団に個人が埋め込まれた状態にはなく、日本独自の文化空間のなかで社会と個人の関係性が作られてきたと考えるのが当然でしょう。阿部はその部分に強い興味を持っていた。
『「世間」とはなにか』は非常に不思議な章立てで「世間」を巡って様々なことが述べられているいるのですが、気になるのは後半の、漱石→永井荷風→金子光晴という流れです。彼らは滞在期間の違いはあっても、当時のヨーロッパを自分の目で見ており、外国語にも習熟してた人々です。さらに言えば、自らの作品、エッセイなどの文章によって、世間から距離を取ろうと試みた人たちだったと言えます。つまり、世間=人間関係に埋め込まれる個人から離れつつ、世間から生まれる人間関係や考え方、社会現象などを独自の目線で見ていた人と阿部は描いています。漱石は小説の主人公を通して、日本の近代化において、個人がうまく世間から開放されないことの複雑性をよく描き出しました。この背景には漱石自身が近代日本における個人について悩み続けたがゆえの結果でしょう。一方で、荷風はフランスかぶれではあるものの、独自な形で日本的世間から離脱しようとした人物でした。面白いのは金子光晴です。ここで阿部謹也は荷風のように外国を理想化し、独自の個人主義をつらぬく人物と対比する形で金子光晴の文章・詩を照会しています。阿部は金子がヨーロッパの深層までよく知ってしまうことによって、荷風のような理想化はできず、西洋人であることのつまらなさを感じたことを書いています。その上で絶望や寂しさを否定しないという態度を紹介して本書は唐突に終わります。
このような終わりに対して、多くの人にとってはこれは結論がないように思われるでしょうし、私もそのように感じました。阿部謹也はこの最後で何を述べたかったのか、それはそれほど単純なことではないでしょうが、私は次のように考えています。日本人に西洋的な個人がないということを問題視し、西洋にあるような強い個人が必要だ、という話になりがちです。しかし、これはこれで話が単純すぎていろいろ問題が出てきます。我々は主体性がなく、西洋をとり得ることを繰り返し、本来の意味での個を獲得することはできない。歴史的な経緯、そこから形成される歴史意識、生活意識が違うのだから、そのまま西洋の個人主義を受け入れることなどそもそも困難であるに違いません。だからこそ、金子光晴が示したある種露悪的な態度について十分に味わい考えてみる必要があるのではないか、阿部が示したことをはそんなことだったかと思います。そしてこれはある時期から私が考えてきたことに重なります。
とあるきっかけで阿部謹也の本を色々読みましたが、阿部謹也はほぼ全ての著作が一貫した問題意識で書かれていて、それは阿部自身が大学生の頃に時代と向き合い、自分の経験と学問的な先達によって作られたものです。学者のなかではアカデミズムの仕事だけしていると、このような問題意識は薄まってくると阿部は考えていた節がありますが、まさに専門領域とは別のところで言葉を紡ぐことの重要性を感じさせる人です。阿部は教育者としても確かな問題意識を持ち、一橋大学の学長を経験、国立大学協会会長の経験などを通して考えたことを残したりもしています。これらの文章はとりとめもないように映るかもしれませんが、私は非常に重要なものではないかと思っています。阿部謹也についてはまたの機会に紹介してみたいと思います。