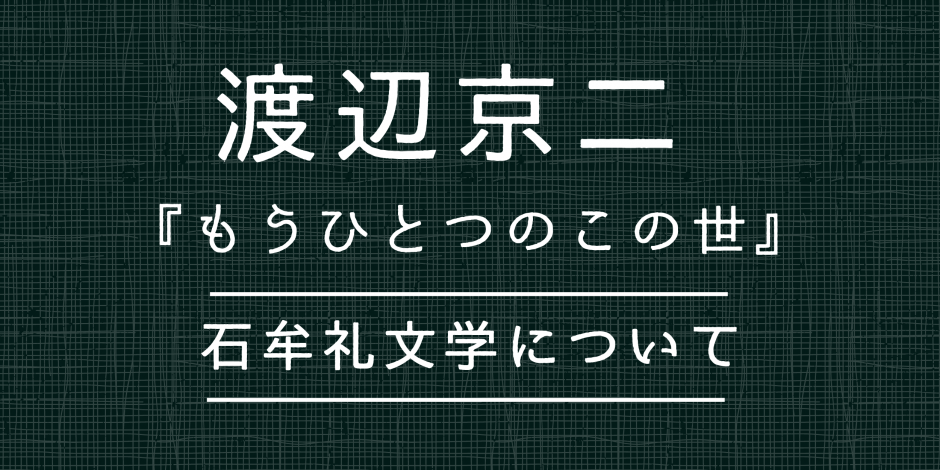私が歴史興味を持っているのはアカデミックな歴史というよりは、現在と過去との関係においての歴史です。現在の我々は過去を物語することによって現在を理解することから逃れることができません。その物語を支える歴史学、哲学、文学や民俗学があるのではないか、そしてその領域にアプローチしようとするときに、アカデミックな領域からどうしても外れざるをえない側面がある。そして、アカデミズムから外れて現在の我々にとっての歴史を扱った人は結構いるように感じます。その点において非常に興味深く読んできたのが、渡辺京二です。渡辺京二は年をとってから熊本大学の客員教授を引き受けたりしていましたが、基本的には編集者、塾講師という職につきながら、執筆を続けてきた方です。 渡辺京二は非常に多面的な人だと思います。日本の近代史については割と細かい記述まで拾いながら、エッセイ的な文章を書いていますが、一方で文学に関しても膨大な知識をお持ちの方のようで、読んでみると細部の記述の鋭さに驚かされることがあります。本になっているのは『私の世界文学案内』くらいか思いますが、文学、そして歴史や思想についても、渡辺京二の書き方は、過去のものを踏まえながら、渡辺個人として書いています。様々文献の内容を論理的に積み上げて論じるというよりは「私はこう考える」的なスタンスで、エッセイ的なものが多いのですが、渡辺京二の文章からはそのスタイルだからこそ書けるものの可能性を感じます。私はもう少し渡辺京二の文学論を読み込んでみたいと常々考えていました。
渡辺京二が文学的な考察のちからを感じたのはやはり石牟礼道子を巡る文章を読んだときでした。渡辺京二は『苦海浄土』が世に出た時に編集者として関わった人物でもあります。苦海浄土の原型となる『海と空のあいだに』は、渡辺京二が編集していた「熊本風土記」に連載という形で載されました。渡辺京二と石牟礼道子はその原稿を載せることから関係をスタートし、その後も密接な関係が石牟礼道子が2018年に亡くなるまで続きます。その意味では私的な関係においても、文学的な仕事においても渡辺京二は石牟礼道子の一番の理解者だったと言えるでしょう。石牟礼道子は『苦海浄土』があまりに有名であり、かつ『苦海浄土』が水俣病という日本でも有数の公害問題を土台にし、石牟礼道子自身も被害者の側に寄り添う形で運動に参加していることから、この作品を触れた多くの人は、そこに文学的な要素を見出すということは稀ではないかと思います。ただただ、不思議な文章力によって、心が動かされるものの、それは水俣病という背景があってのこと、と理解されてしまいます。渡辺京二は石牟礼道子をそういった公害問題のヒロインとしてしまうことに対して抵抗し続けたことは確かです。石牟礼道子には『苦海浄土』の他に小説がいくつかありますが、『苦海浄土』を読んだことをきっかけとして、石牟礼の他の小説を読んでみようと考える人はまれだと思います。 石牟礼文学については『もう一つのこの世』、『予言の悲しみ』の2冊に渡辺京二の石牟礼道子に関する文章が集約されています。『もう一つのこの世』の中の「石牟礼道子の時空」という文章が特に石牟礼文学の特徴を的確に分析しています。ちょっと引用してみます。
先に『あやとりの記』を論じました際に、私は生命に関する原罪感ということを申しました。これはこの世に対する先天的な欠損感と言ってもよろしい。『おえん遊行』を読むと、『あやとりの記』で表出された作者の原罪感・欠損感が、実は近代以前の、いわば中世的な伝統につながっていることを、否応なく悟らされます。作者の近代的な個に刻印された存在のかなしみの根は、前近代の過去の闇に深く降りているのです。 (小略)もっと具体的にいうと、この物語にはいちじるしく能に近いところ、浄瑠璃あるいは説経節に近いところがあります。(渡辺京二『もう一つのこの世』弦書房)
ここでは『あやとりの記』と『おえん遊行』という小説を取り上げて、石牟礼文学の登場人物の特徴について論じています。特に『あやとりの記』は私も好きな作品です。この作品は福音館の『こどもの館』という月間誌で連載されていたもので児童文学として扱われています。登場人物は石牟礼道子の分身であるみっちんの他、乞食や精神に異常をきたしながらも村人に愛されながら、山の中など、村の周辺部で暮らしている登場人物が描かれます。彼らは一様に農村共同体のなかでは暮らすことのできなかった人たちですが、かといって差別民として描かれいるわけでもない。別のいいかたをすると、彼らは農村的のある種強制的な共同性に適合的なかった狩猟採集民的な気質を持っている人々です。石牟礼道子は水俣において、これに類する人たちと交流していたのでしょうが、石牟礼自身は村、そして近代的な制度に順応しながら(石牟礼は学業が優秀だったため学校の先生になっています)、そこに完全に順応して生きられない自分を、これらの登場人物に託し、非常に高度な文学的表現に昇華させたといえる、渡辺京二は石牟礼文学をそのようなものとしてみなしました。このような表現は日本の近代文学が描いてきたものとは根本的に違った性質を持っています。
石牟礼道子のこういった文学性は世界的に見ても特異なところがあります。それ以上に、日本語としてこの表現が残されたことについて私は非常に大きな意味があるのではないかと思います。確かに日本を生きる我々とつながっている感覚だけれども、今はもう完全に失われた感覚として、石牟礼道子の言葉を通して、近代以前に存在した、共感能力が高く、強迫気質ではない、ある意味では純粋な人間性に触れることができるということもできるのではないでしょうか。このことは渡辺京二の最も知られた著作である『逝きし世の面影』に通じるメッセージです。渡辺京二には石牟礼文学、そして石牟礼道子自身を通して、至ろうとした何かが一貫して存在しているように思います。