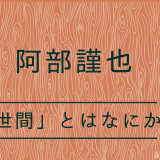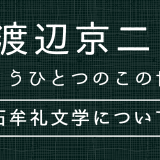以前に柄谷行人を通して「日本」について考えるようになった、そんな感じのことを書いたのですが、柄谷行人をそんな風に読む人は少数なのかもしれません。しかし、柄谷行人は時代や柄谷自身の経験から離れたところで議論をするような人間ではないと思います。それこそ、60年代安保に参加し、現在まで社会運動的なことにコミットしようしていることから現れているように、アカデミックな立場として自分の専門性を狭い範囲に限ってしまうことには批判的でかつ、割と実存的な面も含めて、社会運動から得られる可能性に対する信仰があるように思えました。それは危うさもあるようには感じますが、個人的には柄谷個人に内在している物語には関心があります。全く内的な物語を持ってない人間が書く思想や歴史はやはりつまらないところがありますが、歴史を含めて、自分の意思や理想を突き詰めて考えた結果、高度に物語化され、それがあたかも普遍だと思ってしまうならば、それこそを思想と呼ぶべきなのではないかと感じるからです。
西洋で名前の知られた思想家の言説を、特に自分自身として考える必然性もなく要約しているだけのものは思想とは呼べないように思います。大学で西洋哲学を専門にしている人々の中にも、一部を除いてそういった個人の内面と接続して、思想と向き合ってる部分がかならずあるはずです。そして、その個人的な理由にはある程度実存的な面があり、かつ、その時代を反映したものであると私は考えています。批評家はそういった時代性に敏感であるがゆえに、普遍性とは違ったところで仕事をすることになる。柄谷行人という批評家はまさにそういった時代性を踏まえながら普遍的なレベルでの実存を論じているのだと私は感じています。そして、多くの作家もそういう態度を取りたいと思っている部分があるはずですが、柄谷行人のようには文学や思想を論じることはできません。柄谷は積極的に批評家であることを選択しましたが、この態度、そしてその結果得られた実績は、同じような志向性を持つ人々から尊敬の念を持って受け入れられたのではないでしょうか。
私は文壇の状況にはあまり興味がないのですが、柄谷行人がある種の知的な人々の間では特権的な批評家であったことは理解しています。しかし、それはある時期以降、こういった柄谷行人が本来、批評家を選択したときの志向とは関係ない興味の持たれ方になっていたのかもしれません。文壇で存在感を出すことを嬉しく思う気持ちはだれにでもあると思いますが、柄谷行人はそのような状況に対して苛立ちもあったのではないかと私は推察しています。
柄谷行人の思考のうち、私が気になったのは戦前に対する強い興味です。彼自身が団塊より少し上の世代で、戦争は終わっているのに、特異な意味において戦争という自分が主体的に生きてこなかった状況に縛られていたからかもしれません。80年代生まれの私から見ると、戦争の記憶が曖昧な形で残りつつも戦後しか知らない学生のリアリティは想像するのも難しい。しかし、戦前に対する関心は、柄谷の世代から、我々の世代までどこかでつながることは十分にある。むしろ、それを繋げない限りにおいて、我々は時代の中で考えることなんてできないのではないでしょうか。批評家が文学で思想を論じることで、どんな時代のものでも、現在を”歴史における現在”において語りうるということ。個人的にはそれによってある種のリアリティに到達しようとすることが重要だと考えます。その面で行くと、例えば柄谷行人が「近代の超克」という日米開戦下で開催されたシンポジウムに対する関心と、それを基準に論じていることは非常に興味深く読みました。
「近代の超克」は主に2つの立場について批判されていると柄谷行人は説明しています。一つは京都学派と呼ばれる思想家たちの一部が大東亜共栄圏というファシズム体制を支えた考えを哲学に基礎づけたということ、もう一つは保田與重郎を代表として、戦線拡大を扇動した文学者たちの存在です。例えば竹内好が論じているように、「近代の超克」は戦争とファシズムのイデオロギーを強化することを目的としたと考えられているようですが、柄谷は「近代の超克」はそのような思想形成を目的としてないと述べています。この理由は柄谷がそれまでの哲学・文学の歴史状況を考えると、ファシズム的なイデオロギーに賛同する形でまとまっていくはずはない、ということです。柄谷行人「近代の超克」(『<戦前>の思考』)という文章では「近代の超克」で起こっていることは複数の「美学」の対立であり、ぶつかりあいであったことを示します。日米開戦時においては、西田幾多郎を代表としては京都学派におけるの立場は独自の形でまとまっており、日本浪漫派については保田與重郎がその美学的立場を示していました。これらの立場に加えて、自由主義的な立場をとる小林秀雄などの文学者が参加しており、彼らがお互いの美学的立場を総合して、一つのイデオロギーに向かうということはありえません。「近代の超克」が京都学派や日本浪漫派の戦争肯定的なイデオロギーとして批判されるのはそれが安易だからであり、そのことにあまり意味はありません。では「近代の超克」から何を読み取ることができるのか。それは小林秀雄の態度が、極めて難しい状況ながらもある種の「自由」を模索する態度、京都学派的な解釈への抵抗として見えることと関係があります。日米開戦後という状況は、このシンポジウムに参加した人々にとっては、それほど明るい未来が描けるような状況ではなかったでしょう。よって、このシンポジウムにあったのは西洋的な近代に関する批判と対立であったわけですが、その対立は現在を考える上でも示唆的です。柄谷には京都学派的な美学と日本浪漫派的美学を論じ、それに批判的な小林秀雄の態度を示していますが、最終的にこれらの空虚さについて述べています。しかし、本当の京都学派や日本浪漫派的態度を空虚なものとして切り捨てることができるのか。私は戦後行われてきたのはこれらの美学的な立場から目をそらしてきたことで似たような繰り返しが起こっているのではないかと感じでいます。一方でこのような美学的対立を「全体主義的」という一言で片付けてしまうような態度はむしろ我々の時代の批判的立場の主流となっている気がします。この流れは歴史感覚の喪失と密接に関係しており、それはすなわち批評的な態度の弱体化といえるのではないのでしょうか。柄谷行人はの「近代の超克」論ではそのようには述べられていませんが、戦後が戦前のアナロジーであると考えることの重要性を私は柄谷行人から学んだように思います。
「近代の超克」における美学的対立についてはまたの機会に書いてみたいと思います。