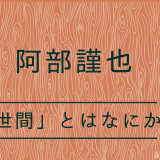前回に続き『アフターモダニティ』について書いてみます。
浜崎洋介さんが昭和初年代の空気感と小林秀雄の批評(≒日本の批評)の始まりについて書いていましたが、『アフターモダニティ』ではその前段として先崎彰容さんが、明治期の文学者を取り上げて、近代文学の誕生と挫折について書いています。二人の書いていることはそれぞれ分析として興味深いだけでなく、それぞれ相互に関係を持っていて、様々なことを読者に考えさせてくれます。その意味でも全体の構想も含めて、非常に優れた本だと思います。
浜崎さんは芥川の「ぼんやりした不安」ものに対する小林秀雄の反応として批評というものを示しました。これは大正期の精神的な特徴を説明していることになりますが、一方で先崎さんは明治期の文学者の葛藤を描いています。昭和に入ったときにはすでに「故郷喪失」というのが後戻りのできないところまで進んでいたとすると、明治期の文学者は、「近代」という西洋からきて自らの内面に入ってきたものをどのように処理していくかということが問題になったいえるかもしれません。これはあくまでの文学者の話ですが、この文化に根差した精神的な安定から、それからは乖離させてしまうような、しかし、資本主義や国家といった、人々の生活を一方で安定させるゆえに受け入れざるを得ない内面への強要があるという図式は、個人の人間にも存在していて、おそらくそれは日本だけの問題ではないでしょう。先崎さんは、明治期の日本が精神的に「近代」を受け入れたことを文学者の葛藤を通じてうまく描いているいえるでしょう。
先崎さんは明治期の日本の文学を説明するときに「ロマン主義」を取り出しています。明治から昭和にかけての精神的傾向に「ロマン主義」を適用することはそれほど珍しいことではないかもしれませんが、今、この時代にその分析をすることの重要性は非常に高いのではないかと個人的には思います。そして先崎さんもそのことを念頭にこの文章を書き、そしてこの本を作ったのだろうと考えられます。
ロマン主義はなかなか捕まえるのが難しい概念です。比較的、ロマン主義を定義しつつ、一方で時代の精神的な特徴を示唆したものにカール・シュミットの『政治的ロマン主義』があります。カール・シュミットは今から考えても非常に重要が議論をしていますが、先崎さんも主にシュミットをベースに日本のロマン主義傾向を分析しています。先崎さんは「ロマン主義は現代社会を生のまま取りだし、理解するための最良の補助線のひとつであり、今こそ見なおされるべき思想なのである。」とはっきり述べていて、私もこれに同意します。さらに先崎さんは日本おけるポストモダン思想のブームについて、無秩序と相対主義を肯定した点においてロマン主義と共通していることを指摘しています。この点に説得力があるのは、ポストモダン思想が、戦後の日本がゆたかさの中で「所属」への関心がなくなったことと密接に関係していて、この点においてロマン主義との共通点が見出されるからです。先崎さんは「所属」への関心がなくなったことが「人間とは何か」という問いに関わる、と述べています。社会が経済的にゆたかになるにつれて、古い共同体に縛られることなく、消費を中心にアイデンティティを形成していくというのが当たり前になっていますが、そのような状況が、それが社会の中で「個」として孤独に存在している「自分」をさせるようなものとして十分なのだろうかという問い、言い換えてもいいのかもしれません。明治期の文学者はこれについて自覚的だったように思います。現在の文学者は商品として自分が書いたものが売れることと、世間的に優れた作家と認められることをクリアしないと生きていけない面があるため、このような本質的な問いから遠いと思います。ましてある時期以降、文学者は基本的に成功者です。明治期の文学者は強い挫折感の生きたと言わざるを得ませんが、今の文学者の挫折感を持ちつづけ、それに向かい合い続けることは非常にまれなことだと思います。ゆえに我々は一度、日本文学が発生したころを眺めてみることは常に重要になってくるのだろうと、私は考えています。
先崎さんが本書で取り上げているテーマはどれも興味深いものですが、北村透谷から石川啄木へという流れを少しだけ紹介しておきます。北村透谷はもはや教科書で名前を聞くくらいの存在になっているかもしれませんが、日本の近代文学の勃興期に詩作と評論を行い、後続の文学に大きな影響を与えた存在のようです。初期の文学者には近代以前の文学的な素養を十分に持っている人々がいますが、透谷もその一人です。そして透谷は近代化によって失われる文学的な土台を意識することで反近代主義的な感覚を持ち、これがロマン主義的傾向として現れてくる、と先崎さんは分析しています。現実が不安定な様相を示しているとき、文学者として、確かな言葉で世界と自分の関係を取り戻したいと透谷は考えた、と先崎さんは述べています。透谷は共通感覚の喪失を問題とした詩人であったといえるでしょう。一方で石川啄木は1868年生まれの透谷に比べれば若く、1886年生まれで、若くして死んだので活動したのほぼ1900年代の後半から1910年代前半のみでした。透谷に比べれば啄木は時代の閉塞感をわかりやすく表現しているように思えます。もちろん啄木の破滅傾向のある性格や境遇などもありますが、先崎さんは啄木自身に積極的に時代を見ようとしたことを捉えます。シニカルで全てに反対してしまいそうな雰囲気を持つ啄木ですが文学への時代的考察については情熱で気でありながら冷静な分析をしています。啄木は活動していたのは明治が終わりに向かい始めた日露戦争の頃(1904-1905年)国家としての日本に帝国主義的な傾向が見えてきたころです。この時期において愛国心というのはただの拡張主義を肯定するだけにすぎず、それまでの過去を支えた歴史を支えるものではない。一方で自然主義文学に代表される文学は、新しく「私」を作り出そうとしてますます分裂していっている。これが啄木が感じた時代感覚です。先崎さんは一見ナショナリスト風に見えながら、どこか日本的な言葉の陰影対して強い感受性を持った啄木が、時代の矛盾と向き合いながら過去からの堆積物を手放さなかったことを日本の「批評」の始まりの一側面としてみているといえるでしょう。
詳しくは『アフターモダニティ』を読んでもらいたいところですが、ロマン主義という反時代性を持ちながらどこかで無秩序化してしまう、その矛盾を見つめつつ、過去と切り離さずにそれを受け入れていく態度にこそ、批評的な態度があるというのはなかなかに興味深い見解だと感じます。